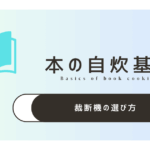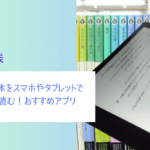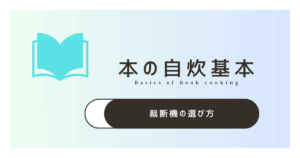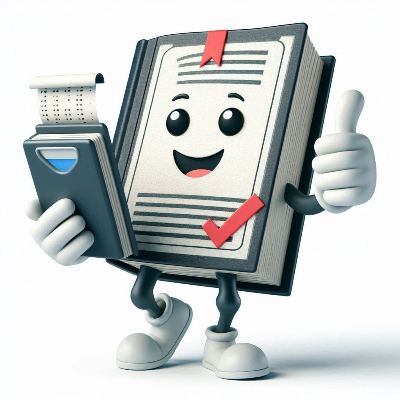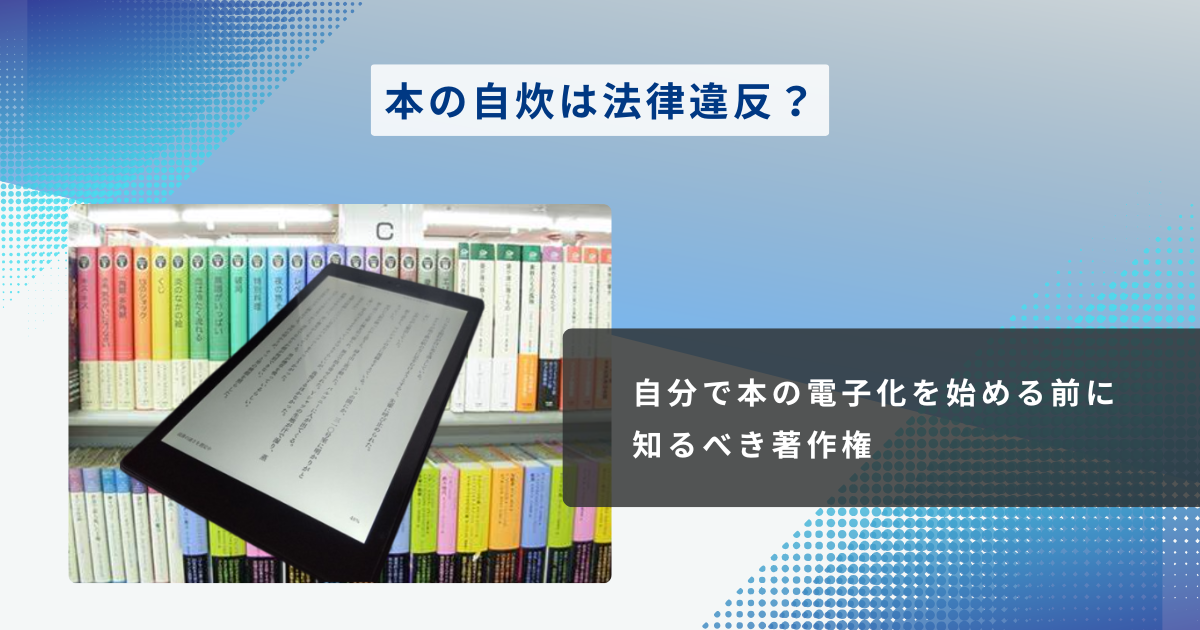
本の自炊と著作権
まず、「本の自炊」とは、一般的に購入した書籍のページを裁断してスキャナーで読み込み、PDFなどの電子データにすることを指します。この行為は、著作物を「複製」することに当たります
著作権法では、私的使用のための複製(私的複製)は例外的に許されています。この「私的使用」とは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」を目的とする場合を指します。
つまり、「本の自炊」に関する法的ポイントは、著作権法における「私的使用のための複製(私的複製)」の範囲で許されるかどうかが鍵になります
では、どのようなケースが許されるのか、逆にどのような行為が許されないのか、具体的なケースを挙げてみます。
本の自炊が法的に許されるケース
本の自炊が法的に許されるというケースは、主に、ご自身で購入した本をご自身が個人的に、またはごく限られた範囲で使用する目的で、ご自身の手でスキャンする行為 です
様々なケースを確認してみます
【ケース 1】
自分で本を購入し、自分で裁断し、自分でスキャンして、そのデータを自分自身だけで利用する
これは著作権法で認められている「私的使用のための複製」に該当します。 例えば、教科書を自炊してiPadで勉強する、漫画を自炊して自分で電子書籍として読むなどがこれに当たります。
【ケース 2】
自分で本のページを裁断する行為
本を購入した後であれば、裁断する行為自体は違法ではありません。
【ケース 3】
代行業者に本の裁断のみを依頼する行為
裁断自体は複製行為ではないため、第三者に依頼しても違法にはなりません。
【ケース 4】
他者から裁断済みの本を購入し、それを自分でスキャンして自己利用する行為
一度公衆に提供された著作物は自由に転売できるという「権利の消尽」の考えに基づき、適法とされています。
【ケース 5】
自炊した書籍をタブレット等で表示し、その場で回し読みする行為
データを表示させる行為自体は複製に当たりません。その場で回し読みするだけでは譲渡や貸与とはみなされないためです。ただし、最初から社内での回覧を目的としている場合は違法となります。
【ケース 6】
スキャンしたデータが保存されたUSBメモリなどの記録媒体そのものを、私的使用の範囲と認められる親密かつ閉鎖的な関係にある友人に貸し出す行為
これはデータの譲渡ではなく媒体の譲渡とみなされ、かつ貸出相手が限られた範囲の人間である場合に限られる、例外的なケースです。ネットなどで知り合った面識のない相手への貸し出しはこれに該当しません。
本の自炊が法的に許されないケース(違法となる可能性が高いケース)
複製主体が自分ではない場合や、複製・利用の目的が私的使用の範囲を超える場合です
【ケース1】
自炊代行業者に本のスキャンやデータ化を依頼する行為
これは、複製行為の主体が依頼者本人ではなく、営利目的の業者であるため、「私的使用のための複製」とは認められず、違法と判断されています。出版社や著作者が自炊代行業者に対して訴訟を起こした例もあります。
ただし、著作者自身がその業者に対して著作権の行使をしないこと(電子化を許諾すること)を明示している場合は、その業者を利用することが適法になる可能性はあります。
【ケース2】
自炊したデータを友人や知人などの他者に譲渡する行為
メールやLINEでデータを送信する行為 は、新たな複製行為を伴い、それが私的使用の範囲外(友人・知人への送信など)であれば違法となります。
【ケース3】
初めから他者への譲渡や共有を想定してスキャンする行為
複製目的が「使用」ではなく「譲渡」とみなされるため、私的複製とは認められず違法となる疑いが強いです。
【ケース4】
自炊したデータを大学のゼミや会社の部署などで共有・利用する行為
業務上の目的での使用は、たとえ内部的な使用であっても「私的」使用には該当しないため、違法となります。
【ケース5】
自炊したデータを販売する行為
営利目的の複製・譲渡となるため、明らかに著作権侵害となります。
まとめ
まとめると、自分でスキャンして、自分だけで楽しむ のが、原則として適法な自炊の範囲です。それ以外の、誰かにスキャンを依頼したり、スキャンしたデータを誰かに渡したり共有したりする行為 は、ほとんどの場合で違法となる可能性があると考えて良いでしょう。
「誰が複製するのか」「何のために、誰が利用するのか」 といった点が、適法かどうかの重要な分かれ目になるようです
これから自炊を始める際は、これらの点を理解し、ご自身の利用にとどめるように注意することが大切です