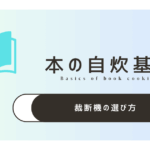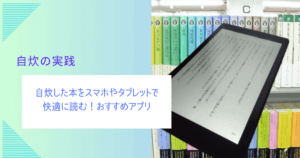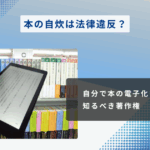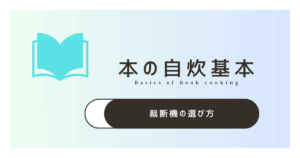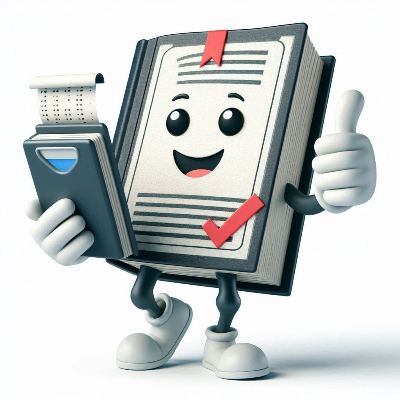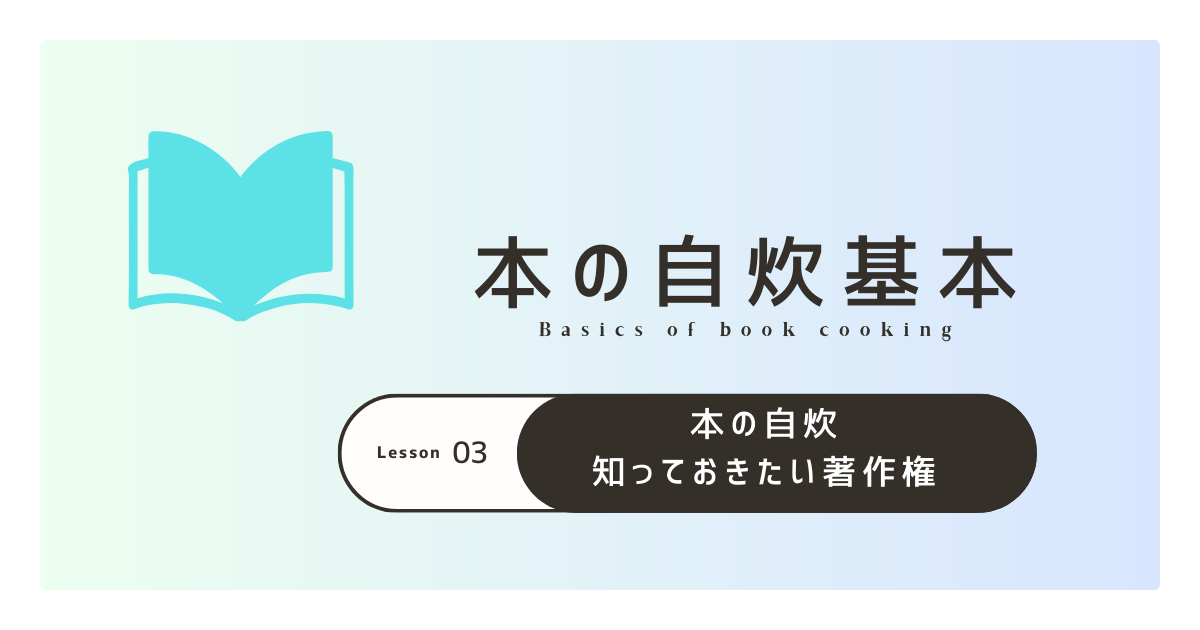
本の著作権について
最も重要なのは著作権です。
著作権法上、著作物を複製する権利は著作者に専有されています。しかし、自分や家族が「私的使用」を目的として本を自炊することは、例外として認められています。
重要なのは、「自炊したデジタルデータは自分だけが楽しむ」という前提です。自炊したデータを本人や家族以外に見せたり、無断でインターネット上にアップロードしたり、販売したりするなどは著作権法違反となります。
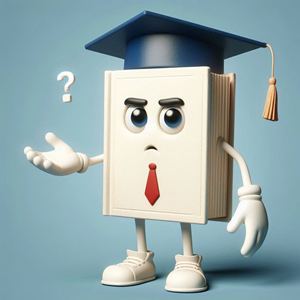
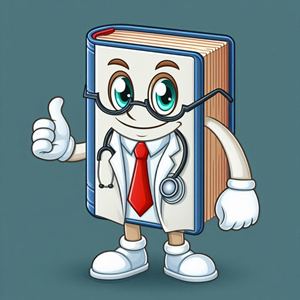
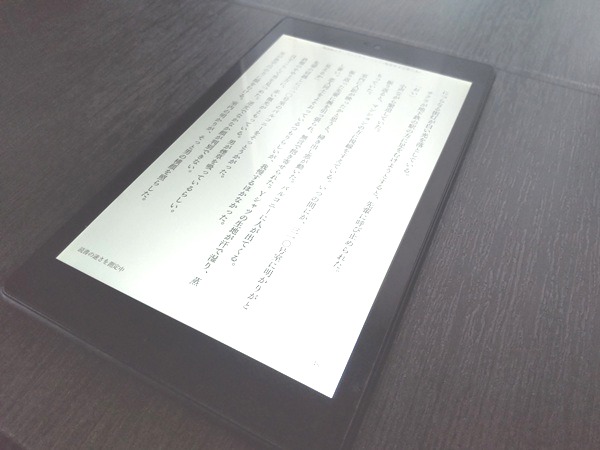
自炊作業の手間と時間
自分で自炊を行う場合、本の分解や裁断、スキャンといった作業にはかなりの手間と時間がかかります。
特に、本をスキャンするためには、まず背表紙を裁断機などで切り落とし、1ページずつバラバラにする必要があります。これにより、元の紙の本は失われてしまいます
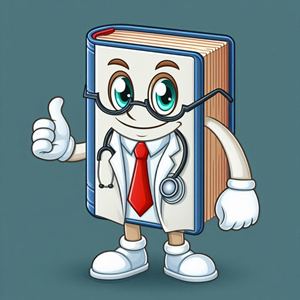
必要な機材と費用
自炊には、本を裁断する「裁断機」と、裁断した紙を読み取る「スキャナー」が必須となります。

その他にも、カッターやエアダスターなどの道具があると便利です。
これらの機材を揃えるには、数万円(スキャナーで3~4万円台~、裁断機で3千円位~)の費用がかかる場合があります。初めての自炊で今後続けるか分からない場合は、機材をレンタルするという選択肢も有効です
完璧を目指しすぎない
自炊を進める中で、すべての本を完璧にデジタル化しようとすると疲れてしまうこともあります。
紙の本特有の質感や匂い、ページをめくる感覚を大切にしたい本は、あえて自炊せず紙のまま残すのも良いでしょう。
人によっては、液晶画面での文字は頭に入ってこないという方もいます。
デジタル化した本を何で見るかにもよります。
スマホやPC、そのデバイスの画面サイズによって自炊に適さない本もあります。
文庫本のように小文字で小さなページをデジタル化して、それ以上の画面サイズのタブレットやPCなどで読むなら、文字サイズも大きくはっきり見えるので自炊した意味があります。
逆にファッション雑誌などの大きなサイズのものを以下の画面サイズのデバイス(例えばスマホなど)で見るには結構きついです。
臨機応変に、自分に合ったやり方で進めることが大切です。
まとめ
本の自炊は、多くのメリットがありますが、一方で手間や費用がかかり、元の本が物理的に失われるというデメリットもあります。また、著作権に関する正しい理解は必須です。
これから自炊を始める方は、こうしたメリットとデメリット、そして注意点を十分に理解した上で、ご自身の読書量やかけられる時間・費用、そして何より「なぜ自炊をするのか」を明確にしてから始めることをお勧めします